未経験から論文系の高度情報処理試験の受験にむけて午後2試験の論文を勉強しているけど、論文を書きはじめるための骨子の作成でつまづくというひとがいるかもしれません。

「未経験からはじめて論文系の高度情報処理試験を受けるんだけど、論文試験の勉強をどうやって進めればいいか悩むんだよな・・」
「はじめて情報処理の論文試験を勉強しているけど、論文を書く準備の骨子をどうやって作っていけばいいのかわからないんだよな〜。。。」

こうした方むけに論文系の高度情報処理試験での論文骨子を作成する勉強の参考情報を紹介します。
当時ははじめての高度情報処理試験の受験でしたが、ITストラテジストという試験区分を選択してなんとか初受験&独学で合格することができました。
そのなかで論文合格の要になったのが論文骨子作成の勉強だったと感じています。
論文系の高度情報処理試験は午後試験のできが合格のキモになりますが、なかでも論文試験はそれまであまり「論文を書く」という経験がないと苦戦する分野です。
ただし論文を書くための骨子の作成を問題なくできるように勉強が進められれば、グッと合格が近づくのではないかと考えています。
未経験からの論文系高度情報処理における論文骨子とは
論文骨子の位置づけ
未経験から論文系の高度情報処理試験を受けるひとにとって、基本的に午後2論文の骨子の勉強は避けて通れない道です。
一番近いイメージは骨組みのところで、自身が書く論文における骨組みを作ることかとおもいます。
受験するひとの中には情報処理試験と関係なくいくつも論文を書いた経験があったり、文章力がずばぬけて高かったりするひとはもしかしたら骨子作成の勉強は不要かもしれません。
しかしそうしたひとでなければ論文試験で2時間で約2000文字を書ききるということを考えると、普通は書ききるための道筋が必要になります。
その論文を書くための道筋が骨子となるため、多くの場合は骨子作成の勉強が必要になってきます。
論文骨子で勉強する重要度
未経験からの論文系高度情報処理を受験するひとにとって、論文骨子は論文を書く道筋となるもので勉強の重要度も高いものです。
論文において骨組みがしっかりとしたものがあれば、多少のブレや歪みが生じたとしても内容的には大きな問題はない論文が書ききれます。
逆に骨子の部分が曖昧だったり、うまくできていなかったりすると、どれだけ肉付けの部分がうまくても主軸がイマイチな論文になり不合格となる可能性が高いです。
そのため骨子のできが高度情報処理試験における午後2論文の合格を左右するといっても過言ではありません。
高度情報処理の午後2論文試験をはじめて勉強しようとおもったとき、勉強内容は3ステップの流れになることが多くなります。
場合によっては不要なステップもあるかもしれませんが、自分がはじめて勉強するときにもこちらのステップで勉強していました。
- 論文材料を準備
- 論文骨子作成の勉強
- 論文を書ききるトレーニング
このうち一番時間をかけるべきで重要なのが論文骨子作成の勉強です。
もちろんひとによって勉強の比重は変わりますし、骨子以外の部分も大事な勉強になります。
しかし筋の通った論文で高度情報処理試験に合格するには骨子作成の勉強における重要度が高いのは間違いありません。
未経験からの論文系高度情報処理における論文骨子の作成
論文骨子の作成による勉強
未経験からの論文系高度情報処理における論文骨子の作成は、論文の道筋と書くことの整理が中心です。
基本的に論文試験では書かなくてはいけないことが問題ごとに用意されています。
それらの必須で書く必要あることと、自身が準備した材料を組み合わせて論文の構成と内容を作ることになります。
最初のうちは骨子を作ろうとおもってもそれほど書けないかもしれませんが、最初は必要最低限だけで各設問で数行程度でも問題ありません。
そこから徐々に慣れと不足する点を準備し直して、肉付けや過不足ない骨子が作れるようにしていくのが大事です。
だいたい論文試験は問題のブロックと設問が紐付いています。
問題に書かれる必要とされる内容、設問で問われている内容を含めて論文を書く必要があり、それらの必要な内容を骨子として作成できるようにする勉強が重要になります。
論文骨子の勉強具体例
ここでは未経験から論文骨子を作成する勉強の参考例を紹介します。
勉強するうちによりよいやりかたなどがみつかったりすでにあったりするかもしれませんので、ひとつの参考になればとおもいます。
令和元年秋期のITストラテジスト試験をもとに骨子作成をどう考えて進めるかという点についてです。
骨子作成では論文の構成も考えますが、基本的には問題、設問通りの流れでよいことも多いです。
とくに最初のうちは、まず書くべき内容をおさえて作成することからはじめます。
書くべき内容は基本的にすべて問題と設問から拾っていきます。
まずは設問アを例に骨子作成をどうすすめるかを考えます。
こちらの問題から書くべき内容を拾っていくと、
- ディジタル技術で解決可能になった事業課題
- ディジタル技術を活用した効率化or品質向上が可能な業務の特定
- 業務プロセスへのディジタル技術の活用で実現する事業課題の解決
という点になります。
次に同様に設問から書くべき内容を拾っていくと、
- あなたが携わったディジタル技術を活用した業務プロセスによる事業課題の解決
- 解決しようとした事業課題と背景
- 事業概要
- 事業特性
となります。
これらが問題と設問から拾えることになり、基本は単純になにを書くように求められているかという観点で拾っていきます。
そしてこれらを組み合わせて書くべき内容と構成を考えます。
大まかな構成は上記通り書かれている流れで、細かい流れの部分で書きやすさや論文の流れを意識して変えたりします。
流れを考えるうえでは基本的には大きなところから詳細に流れるという構成が考えやすいです。
慣れてくれば設問、問題それぞれを読んでから、最初から書くべき内容を拾ったものを組み合わせて書き出せるようにもなってくるとおもいます。
設問、問題から拾った書くべき内容を組み合わせた参考例がこちらです。
- あなたが携わったの事業概要と事業特性
- 事業における課題とその背景
- ディジタル技術を活用して効率化or品質向上が可能な業務の特定
- ディジタル技術を活用した業務プロセスにより実現する事業課題の解決内容
流れも多少書きやすいように変更してだいたいこんな構成になります。
ただし解決内容などの詳細は設問イに続く内容となるため、設問アで書くのはさわりの部分になります。
あとはこの内容に自身が準備していた論文材料をあてはめて考え、内容を作成していきます。
もしここでどうにも内容が考えられない、具体的な内容が書けないというときは、自身が準備している論文材料が不足している可能性があります。
その場合は論文材料の集め直し、準備をする必要あるかもしれません。
骨子として書くべき内容と構成がある程度固まったら、自身の論文材料と組み合わせて具体的な論文骨子を作っていきます。
ここでは例として、ある製造業の会社を用いて考えてみた参考例です。
ただし完全にぱっと見で作った骨子のため、数字や具体例がまだまだ不足した骨子になっています。
実際にはそうしたデータや詳細なども含めた骨子が必要になってきますが、ここでの例は骨子作成の勉強をはじめてみるときの初期状態のものになります。
- あなたが携わったの事業概要と事業特性
→ライン機械製造業の事業
ライン機械は顧客の生産ラインに直結するという事業特性 - 事業における課題とその背景
→検査で機械不良を予め察知する必要がある事業課題 - ディジタル技術を活用して効率化or品質向上が可能な業務の特定
→機械不良の検査にIoT技術を活用してひとの目で察知できない数値レベルの検査業務が可能と特定 - ディジタル技術を活用した業務プロセスにより実現する事業課題の解決内容
→IoT活用による不良予知により生産影響のでる機械不良を防止
かなりざっくり内容の骨子なので、骨子にしてももう少し数値や具体例は必要です。
勉強の初期段階としてはこの程度で、これにもう少し必要なデータ具体的内容を組み合わせた骨子が作れるようになれば、あとは肉付けをすれば論文ができあがっていきます。
データや具体例というのは、たとえば上記でいう事業概要における規模、売上、事業特性や事業課題における数字データ、品質向上の具体的な内容などといった点の内容です。
スポンサードサーチ
未経験からの論文系高度情報処理試験にむけた論文骨子作成の進め方
未経験からの論文系高度情報処理試験にむけた論文骨子作成の進め方は、とにかく最初は量をこなすのがおすすめです。
適当にやりさえすればよいわけでありませんが、まずは慣れも大事なポイントになるためです。
最初のうちは量をこなしていくなかで、どんな内容を書く必要あるか、必要ある点の拾い方、論文材料として準備すべきことや不足していることなどがみえてきます。
そして骨子作成の勉強のなかででてくる不足していると感じるデータや具体例の情報を、論文材料の準備としてどの都度集め直すといった形です。
これを繰返して骨子作成の勉強量をこなしていくと、徐々に論文の精度があがっていきます。
論文系高度情報処理試験の論文骨子を作る【勉強と進め方】まとめ
論文系高度情報処理試験の論文骨子を作る【勉強と進め方】のまとめです。
- 未経験から論文系高度情報処理試験を受験するときの午後2論文試験は論文骨子の作成を問題なくできるように勉強が進められれば合格が近づく
- 未経験からの論文系高度情報処理を受験するひとにとって論文骨子は論文を書く道筋となり勉強の重要度も高い
- 高度情報処理試験における論文骨子の作成は論文の道筋と書くことの整理が中心
- はじめて高度情報処理試験の論文骨子作成の勉強をするときは簡単な骨子の作成から必要なデータや具体的内容を組み合わせた骨子の作成というステップで進めていく
- 未経験からの論文系高度情報処理試験にむけた論文骨子作成の勉強は最初は量をこなして繰返し、徐々に論文の精度をあげていく







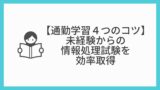


コメント